健康運動指導士が解説|ビタミンD2とD3の違いと、効果の本当の差
ビタミンDは「骨のビタミン」と呼ばれ、カルシウムの吸収を助けるだけでなく、免疫・筋肉・ホルモンバランスにも深く関係しています。 運動指導の現場でも「筋肉や骨を強くする栄養素」として注目されています。
しかし、市販のサプリや肝油ドロップなどを見ると「ビタミンD」と書かれていても、実はその中身にはD2とD3の2種類があります。 どちらを選ぶべきか迷う方のために、科学的データをもとに“運動と健康づくりの視点”から解説します。
1. ビタミンD2とD3は「由来」と「働き方」が違う
- ビタミンD3(コレカルシフェロール):動物由来。魚、卵、肝油、そして私たちの皮膚で日光(紫外線)を浴びることで作られるタイプ。
- ビタミンD2(エルゴカルシフェロール):植物やキノコ由来。紫外線を当てて人工的に強化した食品に多いタイプ。
つまり、D3は「人の体の中で自然に作られる形」、D2は「食品や強化製品で使われる形」です。 どちらも体内でビタミンDとして働きますが、吸収や持続性に差があります。
2. 科学的にみると、D3の方が体に残りやすい
複数の研究やメタ解析では、D3の方が血中のビタミンD濃度(25(OH)D)を上げやすく、長く維持できることが確認されています。
- 同じ量を摂っても、D3はD2の約1.5〜2倍効果的
- 長期的には、D3の方が安定して体内にとどまる
- D2は分解が早く、体に残る時間が短い傾向
簡単に言えば、同じ「1000IU」を飲んでも、D3の方が効果が長持ちしやすいということです。
3. 現場で見る「ビタミンD不足」は、運動効果にも影響する
日本人の多くは日光不足・屋内生活・日焼け止め使用で、実は慢性的にビタミンD不足といわれています。 血中濃度が低いと、次のような影響が出やすいと報告されています。
- 骨密度の低下・骨折リスク上昇
- 筋力低下(特に下肢)や転倒リスク上昇
- 免疫力の低下(風邪・感染症にかかりやすい)
特に高齢者の運動指導では、ビタミンDを補うことで筋力・バランス能力の改善が見られたという研究もあります。 つまり、D3を中心に十分な量を摂ることが、トレーニング効果や転倒予防にも関係しているのです。
4. ビタミンDサプリや食品を選ぶときのポイント
- 成分表で「ビタミンD3(コレカルシフェロール)」と書かれているものを選ぶ
- 植物性・ビーガン対応を重視する場合のみ「D2(エルゴカルシフェロール)」もOK
- 1日の目安量は成人で800〜2000IU程度(体格・生活習慣で変動)
- 上限は4000IU/日まで(厚生労働省・IOM基準)
- 血中濃度を測りながら摂取するのが理想(25(OH)D=30ng/mL以上が望ましい)
サプリを摂る場合は、油と一緒に摂ることで吸収率が上がります。 また、肝油ドロップのような脂質ベース製品は、吸収面で理にかなっています。
5. 健康運動指導士としてのまとめ
運動も栄養も「続けてこそ効果が出る」ものです。 ビタミンDについては、サプリの種類よりも「自分の生活習慣に合うかどうか」が大切です。
- 屋内中心の生活 → D3サプリを活用
- 外で運動する機会が多い → 週2〜3回15分の日光浴で補えることも
- 高齢者・筋力低下予防 → D3を中心に十分な血中濃度を維持
どちらのビタミンDも大切ですが、効率面・持続性・運動効果の観点からはD3の方が優位です。 現場で指導する立場としても、健康維持・筋力維持のためには「D3を主体に、食事+日光+サプリでバランスよく」摂ることをおすすめします。
執筆:健康運動指導士 中村優介
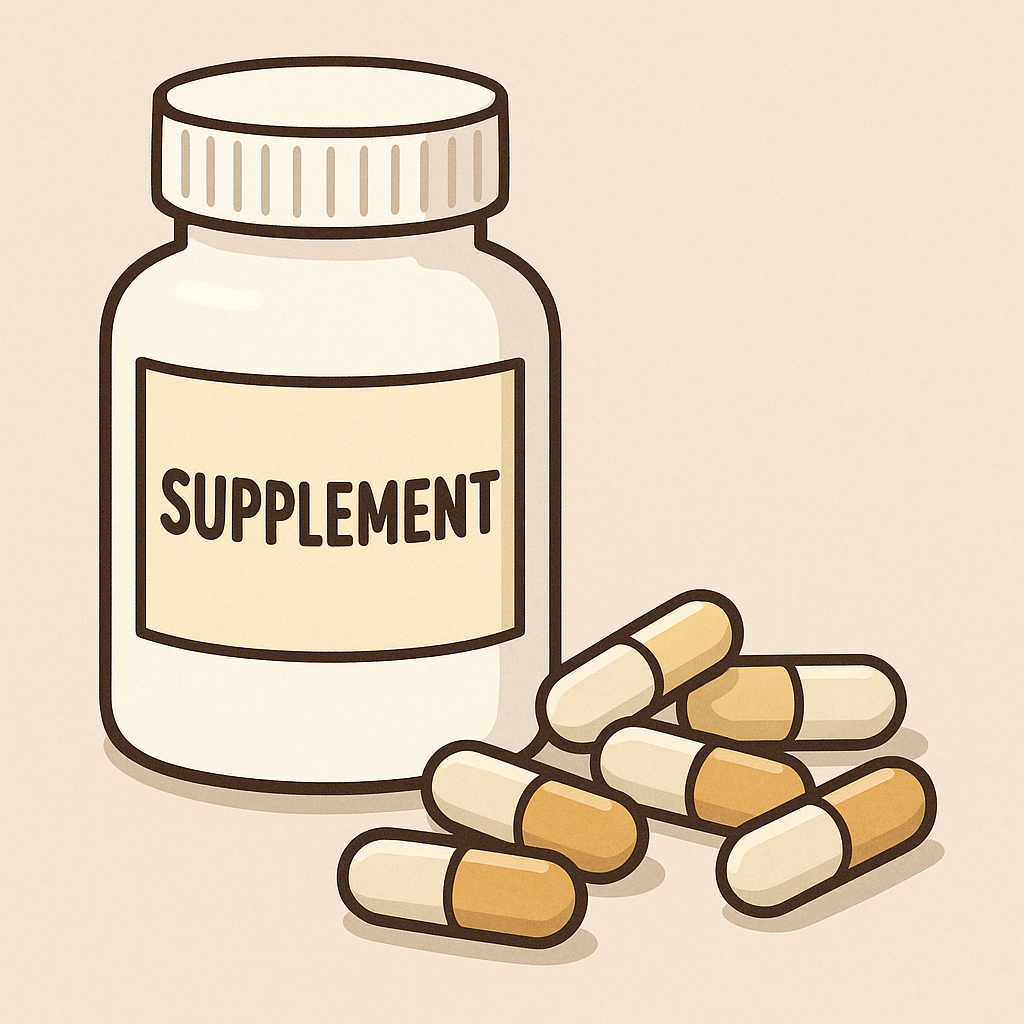
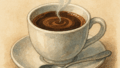

コメント